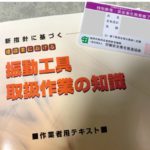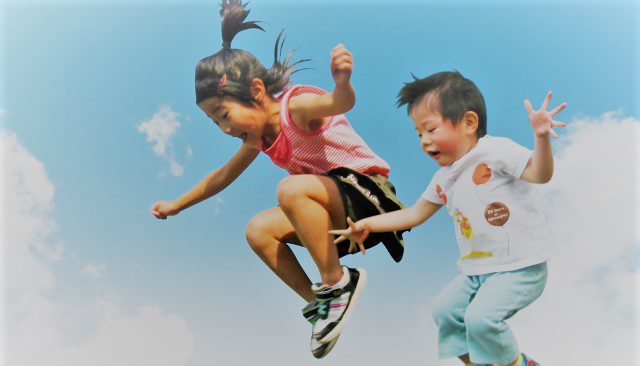
[トレーナー監修]子どもの運動神経を刺激するクリーチャートレーニングについて解説
寒い日や雨の日など子どもを公園に連れていけない時に何をしようか迷うことありますよね。 粘土遊びやお絵描きでも良いのですが、やはり身体を動かした方が昼寝もしやすいですし、 できれば疲れさせたいところ。 この記事では、家の中の少しのスペースで子どもを疲れさせ、なおかつ運動神経を刺激する遊びをご紹介します。 また、その遊びが身体の発達にどう良いのか、スポーツトレーナーの監修で解説します。
![]()
家の中の少しのスペースで子どもを疲れさせ、なおかつ運動神経を刺激する遊びとは?
今回ご紹介する遊びは、「クリーチャートレーニング」です。 聞いたことありますか? 言葉の通り、さまざまな生き物の動きを全身を使って真似することで、身体全体の筋肉を連動させ動かすことできるトレーニングのことです。 検索すると「ライオン」や「フラミンゴ」などいろいろな動物の名前の動きがでてきます。 今回はその中からウチの子がハマった、「スパイダーウォーク」と「クラゲ」の2種類をご紹介します。 ではまず、「スパイダーウォーク」のやり方です。
「スパイダーウォーク」
- 四つ這いの姿勢から、手と足を大きく開く。
- 右手と左足を同時に前に動かし、左側の肘と膝をつけるようにする。
- ②の動作を反対側の手足も同様に行う。
- ②、③の動作を繰り返し行う。
ポイント
- 頭の位置が上下しないようにする。
- 身体の軸をブラさないようにする。
もちろん子どもはこんな風にできていませんでしたが、私の真似をして面白がっていました。 追いかけあっても楽しかったですよ。 このトレーニングには、後ろに向かって進むパターンもあるそうです。 レベルアップしたら挑戦してみましょう! つづいて「クラゲ」のやり方です。
「クラゲ」
- 足を大きく横に広げ、身体の前側に両方の手をつく。
- そのままの姿勢から、右手を左手の前に→左手を身体の後ろ側に→右手を身体の後ろ側に→左手を身体の前方の右側に→右手を身体の前方の左側へと順番に移動する。
- 反対周りも同様に行う。
- カカトを支点につま先を立てながら手を移動させる。
- 膝が伸びたまま行わない。
いや、むずかしい!!! 結局、動画のようにできませんでした。 これは逆にむずかしかったことが楽しかったです! 「あれ?あれ?」と言いながらお互いに尻もちをついたりして笑いこけました。
クリーチャートレーニングを取り入れた習い事
実際にやってみると複雑な動きで身体のいろいろな部分、全身を使っていることが体感できたと思います。
誰も教えてくれなかった運動のコツを解き明かす、「忍者ナイン」というスポーツ教室があります。 やる気スイッチグループ主催の幼児期から学齢期を対象としたスポーツ教室で、特定のスポーツを教育するのではなく、300種類のドリルを組み合わせて身体の連動性を高めてくれます。 私の子どもも入会しているのですが、百獣の王 武井 壮さんの考え方に近いスポーツ教室だと実感しました。 以前、武井 壮さんの動画を見ていると、自分の身体を自分の意志で正確に操ることができればどんなスポーツでも優秀な成績を出すことができるといった趣旨のことを話されていました。
十種競技元日本チャンピオンの言葉なのでとても説得力があります。 私はこちらの動画を見て、子どもに体験させてみることを決めました。 1回の時間が1時間ほどで無料体験は2回させてもらえます。 走る・飛ぶ・投げる・蹴る・競うなどなど、本当にいろいろなドリルを経験させてもらえるので親も勉強になります。 クオリティは教室の広さ、参加している子ども、先生によると感じています。 教室が小学校の体育館やコミュニティセンターの多目的室や市町の体育館の剣道場などいろいろな場所で開催されているので、身近な教室を2か所体験されると良いでしょう。 さまざまなドリルを経験する中で、子どもの好みや長所短所も出てきます。 その子にどんな可能性があるのか「スポーツ適正ナビ」という診断が受けられることも忍者ナインの特徴です。 どのスポーツが向いているのか客観的なデータが提示されるため、忍者ナインの次のスポーツを決めるひとつの参考資料にすることができます。
楽しいだけじゃない!クリーチャートレ―ニングの効果とは?
一見変な動きですが、やってみると意外にむずかしく、大人も楽しめるトレーニングだったと思います。 実はこのクリーチャートレ―ニング、身体の連動性を高める効果があるためアスリートも取り入れているトレーニングなんです。 アスリートに良いなら子どもの発達にも良いハズ! 専門家の監修で身体の連動性について解説します。
身体の連動性について
まず身体の連動性とは簡単にまとめると、「目的に沿った動作を、全身を使って効率よく実現する能力」のことです。 「目的に沿った動作」とは、 「物を投げる」という動作を目的にした場合、単純に物を投げるという事を行うだけならば、手首を軽く振るだけでも実現することができますが、「物をなるべく遠くへ投げる」という事を目的にした場合、手首だけで投げるよりも、肘、肩、上半身の捻り、下半身など全身の力を使って投げた方が遠くに投げることができることはイメージしやすいと思います。 「全身を使って効率よく」とは 「物を持ち上げる」動作を行おうとした場合、物が軽ければ、腕の力だけで持ち上げることができます。 物がとても重たい場合は腕だけでは持ち上がりませんが、腰を落として背筋や脚の力も合わせて使うことで実現することができます。 つまり、身体の連動性を高めることは、より高いレベルでのパフォーマンスが実現できるという事になります。 そしてこの身体の連動性を高めるためには、単に「なるべく重たい物を持ち上げる」「遠くに向かってボールを投げる」と言ったトレーニングよりも、クリーチャートレ―ニングのように身体全身の筋肉を同時に動かせるような動作で、意識しなくても全身を使って身体を動かすことを、身体に覚えさせることが大事になります。
身体の連動性を高める事で怪我の予防にもなる
身体の連動性を高める事は、怪我を予防することにも繋がります。 なぜ怪我の予防になるかというと、本来人間の身体は怪我などによって機能に障害が加わって、ある動作や運動が行えなくなった時、ほかの筋肉の動きで動作を補って目的の動作を実現しようとします。(例えば右足を痛めた場合、右足を庇うために、右足をひきずって歩くようになる代わりに左足に重心を傾けて歩くような動作のこと) よくある例として、
- 裸足で歩く経験が少ない事で、足の指や足裏で地面を掴む能力が発達せず、足の機能が衰え、偏平足になる。
- ボールを投げる際、下半身や上半身の捻りが上手く使えないのに、速いボールを投げようとし、腕だけで投げる癖がつき、結果的に肘や肩の故障に繋がる。
など、これらの障害や故障は、全て身体の能力を上手く使えないことが原因で起こります。 このようにスポーツのパフォーマンスを向上させるだけでなく、故障のリスクを減らすためにも、身体の連動性を鍛えるトレーニングはしっかり取り入れていきましょう!
まとめ
今回は家の中の少しのスペースで子どもを疲れさせ、なおかつ運動神経を刺激する遊びとしてクリーチャートレ―ニングをご紹介しました。 クリーチャートレーニングには、今回紹介した物以外にも「イモムシ」や「ヒトデ」など様々なものがあります。 身体の連動性は、スポーツだけでなく日常動作でも非常に大切な能力です。 ぜひいろいろなものにチャレンジして、大人は運動不足の解消!休日を子どもと楽しく過ごしましょう。
AI搭載全自動除菌ロボット!最新除菌グッズ【ROCKUBOT】
![]()
太陽の1600倍の力の強力な紫外線(UVC)ライトと超音波のW作用でウイルス・細菌・ダニを徹底除菌。 手のひらサイズのコンパクト除菌ロボットです。 超音波はマットレスの奥深くに潜むダニの除去にも効果的。日本の検査機関でダニの増殖抑制効果も認められています。 化学薬品を使わない除菌方法なので赤ちゃん・ペットにも安心。 全自動モードではベッドや布団・ソファー・カーペット・テーブルなどを全自動で除菌することができます。 手動モードにワンタッチで切り替えができ、スマホ・枕・ドアノブ・パソコンキーボードなど 身の回りのものすべてを除菌可能です。 USB充電式なので繰り返し使うことができます。 軽量・コンパクトサイズなので旅先・外出先にも持ち運ぶことができます。 保育園・病院にも導入されています。 メーカー1年保証付きが嬉しい商品です。